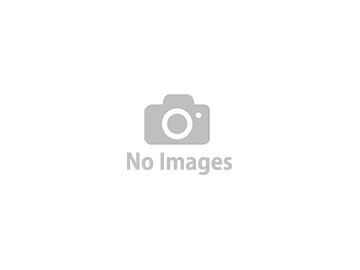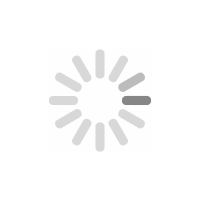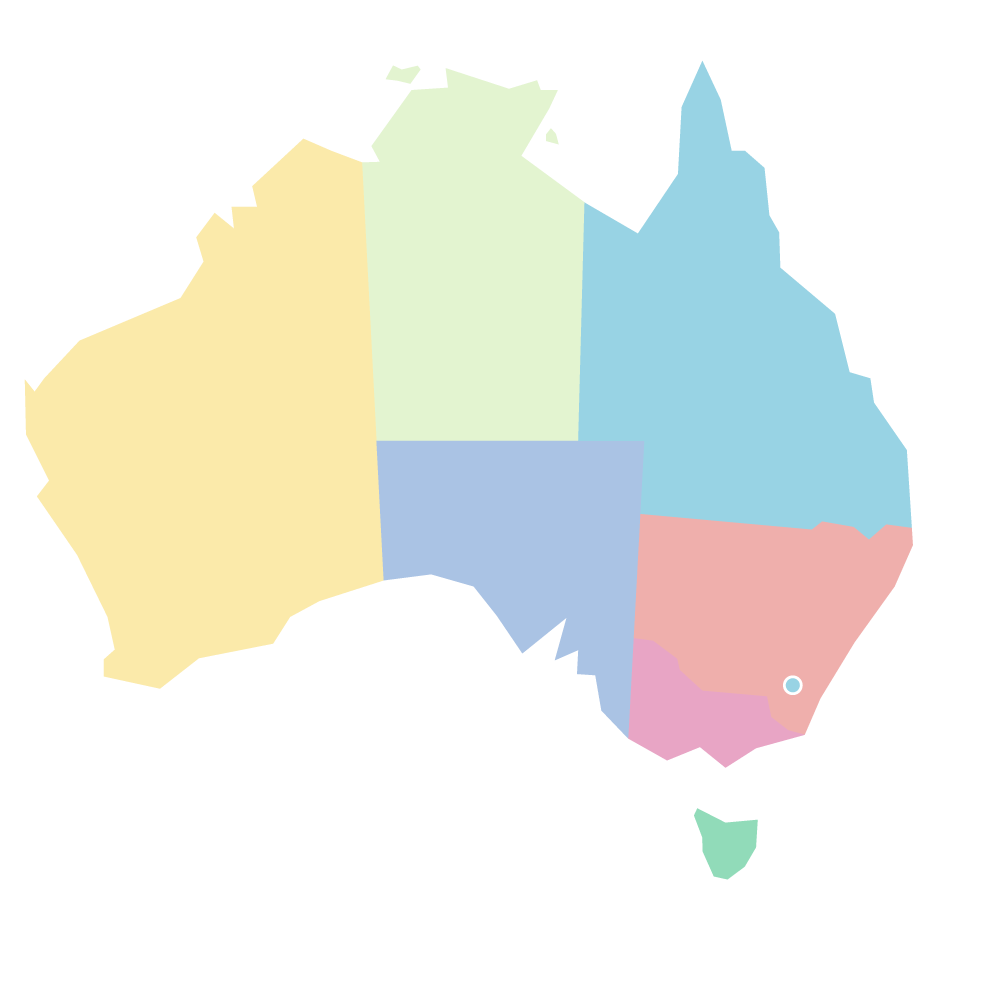13「にごり酒とは」
13「にごり酒とは」
日本酒が日本国内で定められている定義の中に「米と米麹を発酵させこしたもの」というものがあります。日本酒は「もろみ」のままでは日本酒と定義されませんので、必ず「しぼる」必要があります。と前回のコラムで書かせていただき、日本酒のしぼり方についてお話させていただきました。
日本酒の定義上、「酒」の部分と「酒粕」の部分の両方を出さなければいけないというわけで、だいたいの酒粕のパーセントは25%から40%くらい出ます。これが大吟醸とかの超低温発酵のものになると50%を超える酒粕が出ることもあります。
そんな中で、「にごり酒」とはどのようなお酒になるのでしょう。にごり酒はもろみを荒くしぼる方法が取られており、日本で最も有名なにごり酒の蔵は、京都の「月の桂」さんです。この蔵は、上記の酒税法の解釈からのにごり酒の定義を確立させた素晴らしい蔵でもあります。
にごり酒は、通常「ヤブタ」や「ふね」といったしぼり機でしぼる前に、ザルや網などの目の粗い器具を使い、荒くしぼったお酒が多いです。ただ、酒粕は酒税法上出さなければいけません。にごり酒をしぼっていると、この酒粕の量がかなり少なくなります。
また、このように「荒くしぼる」方法以外では、「ふね」や「雫しぼり」で最初にほとばしり出てくる1番しぼりの部分がにごっていますので、その部分だけを別に囲ったお酒もあります。よく「あらばしり」といわれる部分になります。
通常、「ヤブタ」ではこの「あらばしり」の定義が難しいのですが、「ふね」や「雫しぼり」では薄くにごっている最初の部分を「あらばしり」として定義できます。澄んで来たところを「中取り」と言います。
この昔からの薄くにごった「あらばしり」ですが、最近ではほとんど見ることが出来ません。もう1度タンクに戻してしぼりなおしてしまうからです。南部美人ではあまりにもこの部分がおいしすぎるため、8年くらい前から商品化しています。「大吟醸初ばしり」といい、2月と3月限定販売のお酒です。毎年桜の花の時期に重なるので、花見をしながらこの薄にごり酒に桜の花びらを浮かべて風流を楽しみながら飲んでいます。海外での販売は数が非常に少ないため難しいかもしれませんが、いつか試飲会などに持参したいと思います。楽しみにしていてください。