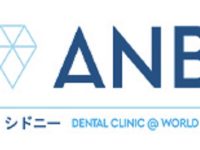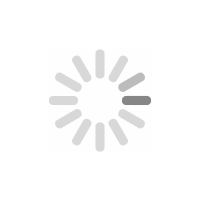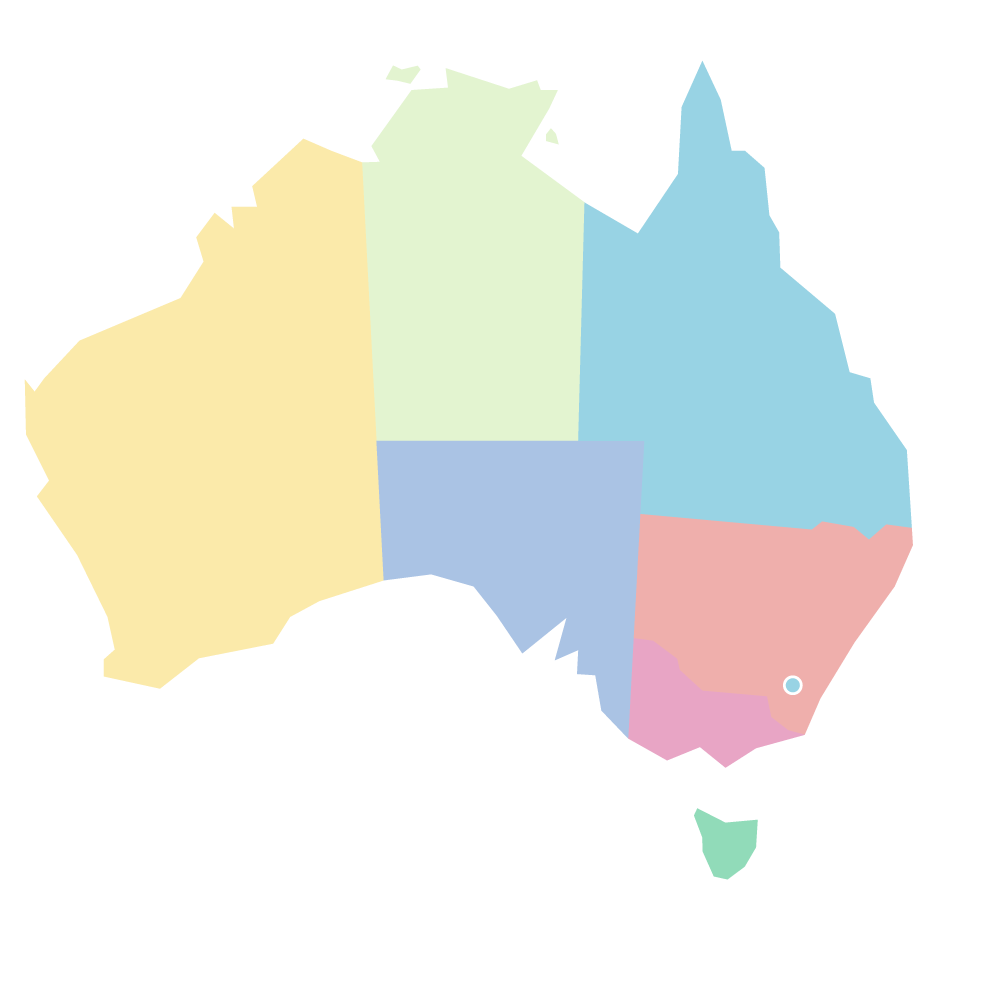18「火入れについて その1」
18「火入れについて その1」
今回はお酒の火入れについてお話したいと思います。
以前もコラムで書きましたが、日本酒には防腐剤が入っておらず、殺菌は火入れと呼ばれる熱殺菌で行なわれます。
日本酒を腐らせる菌は「火落ち菌」と呼ばれ、乳酸菌の一種です。この菌を殺菌することと、生酒の酵素を止めて安定した熟成をさせることを火入れは目的にしています。
火落ち菌は60度以上の温度で殺菌できることから、通常は62度から65度の温度にお酒を加熱し殺菌します。
あまり高い温度になりすぎるとお酒の風味を壊してしまうため、なるべく65度で火入れをしております。
この火入れですが、フランスの細菌学者ルイ・パスツールが発見した低温殺菌法が有名ですが、日本ではそれより前の室町時代の1400年代に火入れの技術を考案していたとも言われております。昔の日本人の知恵には驚かされます。
さて、火入れは「本火入れ」と「出荷火入れ」の2回通常は行なわれます。本火入れとは、しぼった生原酒に対してする1回目の火入れです。通常の方法はタンク火入れと呼ばれ、蛇管かプレートヒーターでお酒の温度を上げて、それをタンクにホースで持って行き、タンクが満タンになったら水をタンクにかけて冷却いたします。
それ以外の方法としては瓶貯蔵用火入れがあり、こちらはしぼったお酒を一升瓶や720ml瓶に詰めてしまい、そのまま湯煎で温度を約65度まで上げて、その後水をかけたり、大型扇風機で風を当てたりして急冷却する方法があります。
タンク火入れは大量のお酒を火入れできる利点がありますが、味の面で劣化が激しいという悪い面があります。
逆に瓶貯蔵用火入れでは味の面で非常に劣化が少ないという利点がありますが、少量のお酒にしか対応できない点、貯蔵に場所を取るという点で不便なところがあります。
この当たりの詳しいお話については次回書きたいと思いますので楽しみにしていてください。
この投稿者の記事一覧
その他の記事はこちら
ワーホリから学生ビザへ!失敗したくない人のための学校選び「U...
予算・時間割・ビザ... 全部妥協したくない方必見! 突然ですが、こんなお悩みありませんか? 「今のオーストラリア、…
矯正前の精密検査と治療プランが重要な理由 😊♦♦
◆ www.haisha.com.au – General, Implant, Cosmetic & Invisalign Total Dental Care ◆ 矯正前の精密検査と治療…